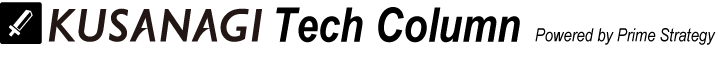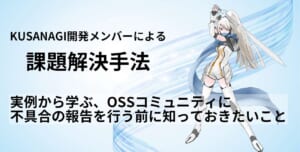人工知能ブームの変遷
現在、さまざまなところで人工知能が話題になっていますが、今回の人工知能への期待の高まりは、初めてではなく、一般的に「第3次人工知能ブーム」と呼ばれています。
1950年代に「第1次人工知能ブーム」が起こりました。1956年のダートマス会議の研究発表会で、ジョン・マッカーシー氏によって、「人工知能(Artificial Intelligence)」という用語が使用されたのが始まりだと言われています。また、この会議でアレン・ニューウェル氏とハーバート・サイモン氏がデモンストレーションを行った“Logic Theorist”と呼ばれる数学の定理を証明するプログラムが最初の人工知能プログラムとされています。
その後、1980年代になると「エキスパートシステム」が注目されました。それが「第2次人工知能ブーム」です。「エキスパートシステム」とは、人間の専門家の意思決定をエミュレートするもので、知識によって複雑な問題を解くよう設計されており、通常のプログラムのように手続きによって、処理されるものではないシステムです。そのころ、日本では通産省が550億円をかけて行った「第五世代コンピュータプロジェクト」が1982年に立ち上がりましたが、それほど成果を上げることもなく、1992年に完了しました。
第3次人工知能ブームのキーワードは
「ディープラーニング」
そして、現在は「第3次人工知能ブーム」なのですがキーワードは、「ディープラーニング」です。「ディープラーニング」とは、多層構造の「ニューラルネットワーク」を用いた機械学習のことです。「ニューラルネットワーク」とは、人間の脳の神経回路の仕組みを模したモデルです。では、なぜ「ディープラーニング」が注目されるようになったのでしょうか?
ディープラーニングの有効性を示す事例とソフトウェアの充実
1つ目は、2012年のILSVRC(ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge)という画像認識のコンペティションでした。たくさんの画像をコンピュータに分類させ、その精度を競う大会で、ディープラーニングを活用したトロント大学のヒントン教授率いるチーム(“SuperVision”)が2位以下に圧倒的な差をつけて勝利しました。
また、2012年にGoogle社内の研究開発部門であるXLabが、YouTubeにアップロードされている動画から、ランダムに取り出した200×200ピクセルサイズの画像を1,000万枚用意しました。画像の中には、3%前後の画像に人間の顔が含まれていたようです。また、猫が含まれる画像もたくさんあったようです。これを用いて1,000台のコンピュータで3日間かけて学習を行った結果、人間の顔、猫の顔、人間の体の写真を識別できるようになりました。
このような事例が出てくることによって、ディープラーニングの有効性を再認識し、期待が高まっていきました。しかしながらそれだけではなく、実はインターネットの発展により、データを容易に収集することができるようになったこと、そしてビッグデータを取り扱う基盤となるソフトウェアが充実してきたというのが、2つ目の大きな要因ではないでしょうか。
Linux Foundationが人工知能、機械学習のための団体を発足
すでに、さまざまなディープラーニング用のフレームワークがオープンソースとして公開されていますが、2018年3月に、Linux Foundationは、人工知能や機械学習の分野においてオープンソースによる変革を促進させるための団体である「LF Deep Learning Foundation」を発足させました。この団体の最初の公式プロジェクトは、AIのモデルとワークフローを開発、発見、そして共有するためのプラットホームである「Acums AI Project」で、2018年11月にリリースされています。その後もホストするプロジェクトが増えており、現在分散型機械学習フレームワークである「Angel ML」などの4つがインキュベーションプロジェクトとして登録されています。
このように人工知能に関連するOSSは多く公開されており、これらを活用することでさまざまな企業の技術者や研究者を巻き込んだエコシステムの形成が人工知能ビジネスの成否のカギを握っていると言っても過言ではないかもしれません。
(※)本文中記載の会社名、商品名、ロゴは各社の商標、または登録商標です。